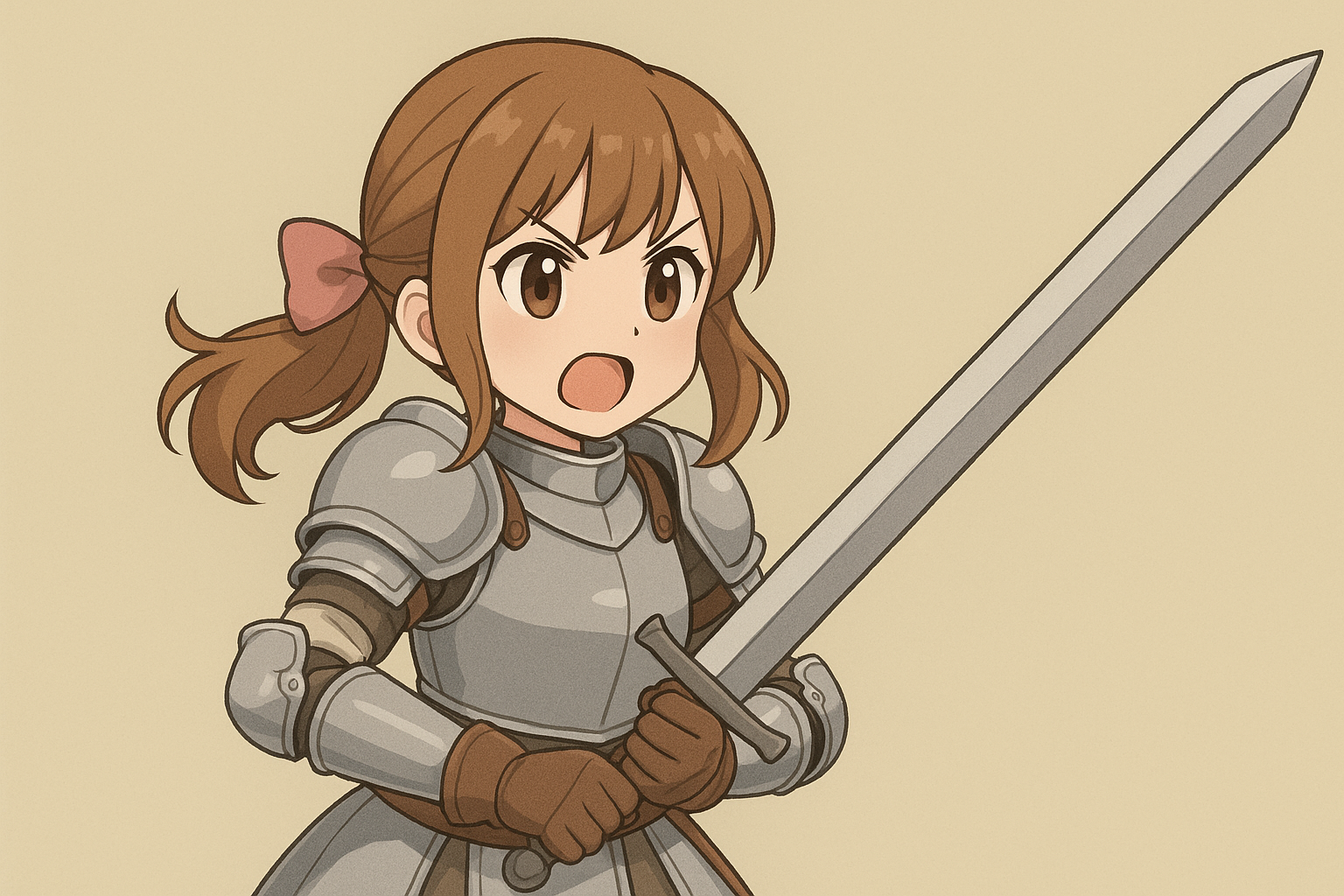
鎧を脱ぐ日
土曜日の午後。机の上には、論文という名の未完成建築が、レンガのように積み上がっている。それなのに、私の指はなぜか、この取るに足らないエッセイとも呼べぬ文字の群れへと向かっている。研究者という仮面を被った私の眼が、その仮面の隙間からこぼれ落ちる埃のような言葉を拾い集めている。これほど不条理な行為があるだろうか。
研究者として積み上げたキャリアは、今日に限って砂の城のように脆く感じられる。論文という構造物を築くうちに、私は「私」という礎石をどこかに置き忘れてきたのではないか。この疑念が、骨の髄まで沁みる。論文という領域は奇妙だ。そこでは「私」という存在が、まるで禁じられた物質のように排除される。主語は「本研究では」に置換され、感情はエタノールで拭き取られ、無菌室のような様相を呈している。思考の微生物を殺菌した言葉だけが、冷たい照明の下で許容される空間。私はそこで、透明な幽霊のように振る舞うことを強いられてきた。
エッセイは違う。エッセイはむしろ、鎧を脱ぐ儀式の場だ。ここでは、私が私であることが許される。いや、強制される。不完全な思考の継ぎ目、矛盾という名のほころび、時として脈絡なく散らばる感情の破片、それら全てを、胸を張ってさらけ出さねばならない。ここには免罪符はない。あるのは、裸の精神が床に落とす影だけだ。
知識を語ることに、私はほとんど躊躇しない。それは安全地帯だからだ。学問という闘技場では、論理が剣であり盾である。感情は、戦場には持ち込めない荷物だ。「正しさ」を主張することは、鎧の輝きを磨く行為に等しい。たとえ論理に亀裂が入っても、それは単なる「修理される傷」として処理される。コンピュータのバグが修正されるように、静かに葬り去られるだけだ。
しかし、弱さは違う。弱さを曝すことは、城壁の外で鎧を脱ぐことに等しい。それは単なる武装解除ではない。鎧そのものが皮膚だった者が、自ら表皮を剥ぎ取るような行為だ。長年、論理という名の鍛冶屋で打ち固めてきた甲冑は、もはや外装ではなく、思考の皮膚そのものとなっている。それを脱ぐとは、生きた神経を剥き出しにし、理論で覆い隠してきた生身の脆弱性を晒け出すことに他ならない。
床に落ちた生卵が二度と殻に戻らないように、露出した内実は取り消し不能だ。傷ついたと告白すること、妬みという毒を口にすること、届かぬ星を指さし続けることは、鎧の継ぎ目から滲む「私」という原液を、自ら溢れさせる行為である。例えば、鎧を纏わずに不格好に歩くとは、鍛え上げた論理の筋肉を解き、歪んだ骨格を曝け出すことにほかならない。誰も見ていないと分かっていながら、その無防備さがもたらす気恥ずかしさの奥には、鎧が染み込ませた防衛本能が「危険だ」と警告を発している。私たちが弱さを晒すことに無意識の罪悪を感じるのは、自らが構築した生存システムへの叛逆であり、武装せよと命じる内部の警鐘を無視する戦慄ゆえなのだ。
しかし、それでも、人生の最も深い共鳴は、傷口と傷口が触れ合う時に生まれるのではないか?と私は信じている。完璧な仮面同士が向き合っても、そこに生まれるのは冷たい反射だけだ。光が内側へと浸透するのは、むしろひび割れた部分を通してなのだ。
論文が世界への宣言であるなら、エッセイは誰かへの密かな手紙だ。その「誰か」が実在するかは重要ではない。過去の自分かもしれないし、未来の見知らぬ誰かかもしれない。肝心なのは、筆者が一つひとつ、鎧の留め金を外していくプロセスそのものにある。言葉が甲冑から解放され、生身の温もりを取り戻す瞬間にある。
人を真に動かすのは、整然とした知識の陳列ではない。隙間なく 組み上げられた結論の城壁でもない。むしろ、不意にこぼれた「実はね…」という呟きのほうが、誰かの胸の奥で共鳴することがある。夕暮れの帰り道、友人が突然、本音を滲ませ始める時のあの親密な距離感であり、時には危ういほどの近さである。
消毒されていない言葉は、時にぎこちなく響く。しかし、その不器用さの中にこそ、理解の種子は埋まっている。鎧を脱いだ言葉だけが、同じく鎧を脱いだ心に届くのだ。
土曜日の午後。論文の締め切りは視界の外へと押しやられ、キーボードの上で指だけが動いている。この生産性から見放された行為こそが、肩から重い甲冑をそっと下ろしてくれる。無菌室の外で、私はようやく息をついている。剥き出しの心が空気に触れる。ひりつくような自由を、私は噛み締めている。