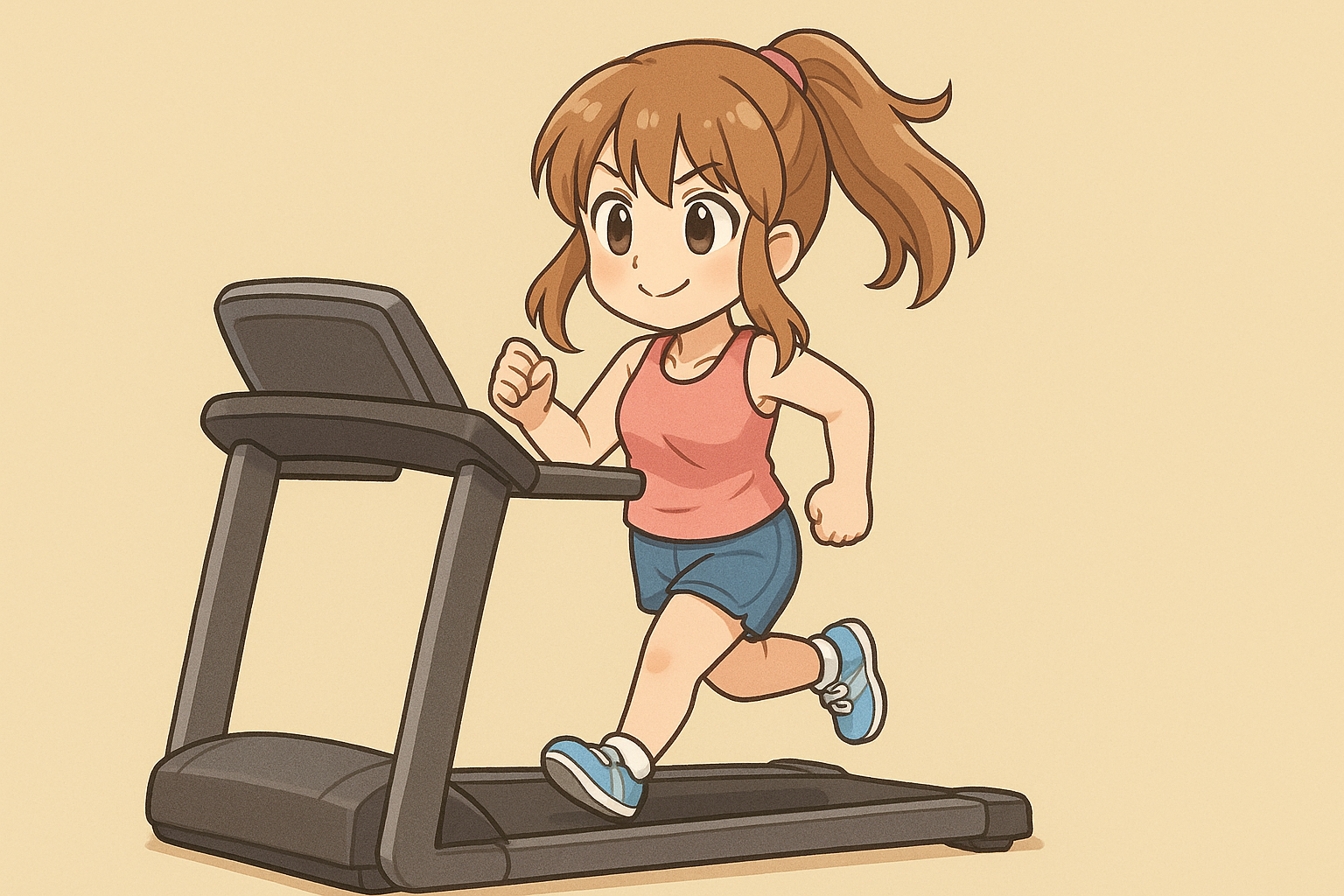
トレッドミルのすゝめ
僕は走る。だから僕は存在する。
窓の外で雪が降る。音もなく、意味もなく、ただ白い沈黙を積み重ねていく。北国の冬は哲学者のようだ。残酷なまでに正直で、一切の慰めを与えない。外に出れば、世界は白い原稿用紙になる。僕の足跡はそこに書かれた文字のようで、しかしすぐに消えていく。シューズは滑り、大地との対話は曖昧になる。これは走ることなのか、それとも白い虚無との交渉なのか。
雪の上を走るとき、僕たちは皆、サイレント映画の俳優になる。声は届かず、動作だけが意味を持つ。転ばないように身体は縮こまり、やがて走ることは祈りに似てくる。
去年の冬、僕は降伏した。走ることをやめ、代わりに本の海に潜った。この世の全てが嫌いになるぐらいうんざりな経験だった。
しかし今年、僕は機械の上で走ることを覚えた。トレッドミル。それは走ることの翻訳装置だ。本物の大地をベルトに、本物の風を空調に、本物の風景を壁に置き換える。
最初は屈辱的だった。まるで檻の中のハムスターといえば可愛げがあるものだが、そんなものではない。
しかし三ヶ月が過ぎ、月に四百キロメートルという数字が積み重なるうちに、僕は理解し始めた。これもまた、走ることの一つの形なのだと。そして、気がつけば僕はすっかりこの翻訳装置が気に入り始めていた。
機械は優しい。アスファルトのような暴力性はなく、雪のような裏切りもない。洗練された指揮者のように美しい律動を作り出し、ただ静かに、確実に、僕の歩みを受け止めてくれる。
そして、天候という独裁者からの解放。軽やかな衣服という自由。計画通りに走れるという、ささやかな確実性。これらは単なる利便性を超えて、ある種の尊厳を与えてくれる。
だが代償はある。それは退屈という名の虚無だ。
変わらない風景。変わらない音。変わらないのだ。何もかも。 時間は粘土のように重く、意識は宙を漂う。人々は問う――「退屈ではないのか」と。
愚問である。僕は様々な方法でこの虚無と戦った。
まず、音楽だ。音楽は時間に色を与える。しかし音だけでは足りない。それは料理の下味のようなもので、それだけでは完成しない。
朗読を試みたこともある。ヴォネガットのタイタンの妖女という、宇宙的な皮肉を聞きながら走ったこともある。だがそれは、葬式でジャズを演奏するようなものだ。僕は Audible をその日に解約した。
動画という視覚的な刺激は案外良い。他者の真剣勝負を眺めながら、自分もまた何かと戦っている気になれる。孤独が少しだけ薄まる。
しかし最も深い体験は、何も求めないときに訪れる。音も映像も言葉も捨て、ただ呼吸と足音だけになるとき。意識が透明になり、時間が液体になる。僕はこれを「解脱」と呼ぶ。宗教的な意味はない。ただ、他に言葉が見つからないだけだ。
三ヶ月後、僕はマラソンを別人のように速く走れるようになった。それが機械のおかげなのか、僕の中の何かが変わったのか、それはわからない。
走ることとは結局、無数の「わからない」と踊ることなのかもしれない。
外では今も雪が降る。明日も僕は機械の上を走るだろう。その単調な繰り返しの中に、また新しい何かを見つけるかもしれない。あるいは何も見つからないかもしれない。
それでもいい。走ることそのものが、すでに答えなのだ。何かが始まるとき、それはいつも静かだ。