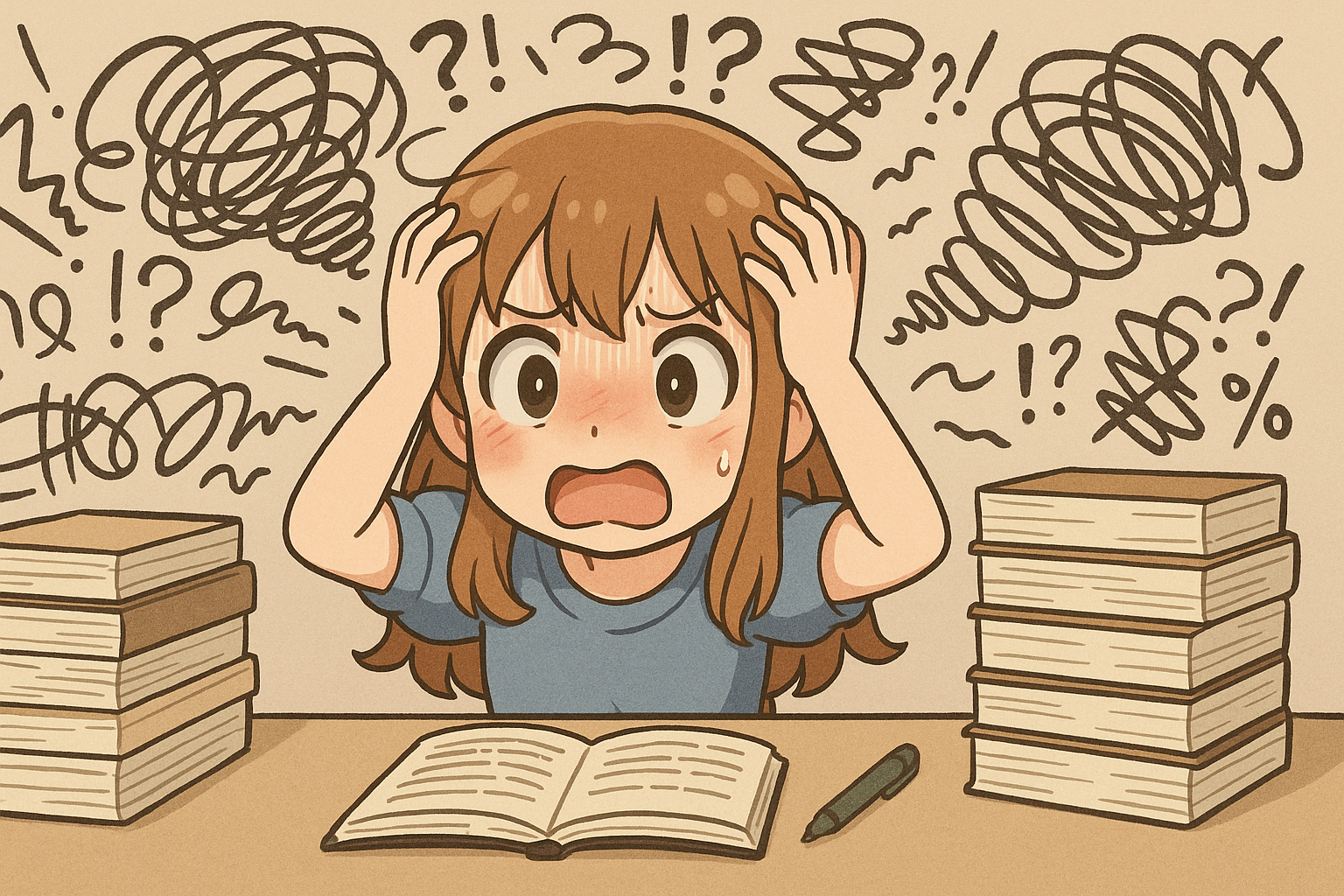
削ぎ落とされた迷い
僕は科学者だ。
正確には、科学の世界に身を置く中年の男。だが「科学者」という響きには、実験ノートの余白に描かれた一筋の希望のような軽やかさがある。僕はそうした微かな輝きを、少し大切にしている。
朝、いつものように豆を挽く。金属の歯車が噛み合う唸り。粉は焦げた星屑のようだ。 立ち込めた香りをいっぱいに吸い込み、慣れた手つきで濾過器を配置してお湯を注ぐ。湯気がベールのように立ち昇る。何気ないルーティンの一つ、コーヒーを淹れるという行為が、荒れ狂う思考の海に錨を下ろす儀式のように、無数の選択に苛まれる一日へ向かう前の、最終防衛線のように感じられる。この数分間だけは、世界が「選べ」と迫ることをやめたように感じられる。
睡眠は取った。体は動く。散歩もランニングもする。それでも脳髄の奥底で、何かが静かに削れ続けている。使い古した消しゴムのように形骸は残っても、角は丸くなり、表面はガラスのように滑って、痕跡すら残さなくなった。
古い論文を捲るとき、奇妙な時間の渦に飲み込まれる。誰かが鉛筆の芯で血を滲ませながら築いた数式の城塞が、今や import numpy as np という現代の呪文で一瞬に灰燼に帰す。二十世紀の誰かが数週間かけてたどり着いた真理の頂に、僕の指先がワンクリックで触れる時代。
それなのに、僕たちは昔よりも深く、重く沈んでいる。
答えは明快だ。脳が溶鉱炉のように過熱しているのだ。
この器官は、一日に数百もの分岐路を処理するようには進化しなかった。かつての世界は二つのボタンしか持たなかった。白か黒、進むか止まるか。しかし、今や眼前には無限のグラデーションのメニューが広がり、朝から晩まで「選べ」と無言の圧力をかける。便利とは選択肢の増殖であり、その増殖とは疲労の堆積だ。選べるという特権が、選ばねばならぬという刑罰へと変容した。
「最近の若者はタフネスが足りん」と呟く重役の銀縁眼鏡が、ちょうど自動化推進プロジェクトの承認印を押している。皮肉の二重螺旋だ。彼の青春を彩ったのはタイプライターの行送りレバーという単純なスイッチだけだったのに、今や我々は Slack の通知という鞭に打たれ、Notion のタスクツリーという迷宮に囚われ、Google Docs で共同編集されるバラバラの人格パズルを必死で組み立てている。
それは進歩という名の不可逆反応だ。悪くはない。だが、我々がまったく異なる生態系に生きている。
夕暮れ、研究室を出て。僕は頭の中で「考えるのをやめる」沈黙の実験を始める。信号の色の変わり目を、ただ光の粒子として視る。風の音を、空気の振動そのものとして聴く。木の葉の揺れを、解釈を介さずに網膜へ落とし込む。
脳のエネルギーは、常に臨界点すれすれだ。僕たちは「働きすぎている」のではなく、「思考の洪水」に溺れている。
効率化が生み出したのは自由な時間ではなく、高濃度に濃縮された「判断」という名の放射性廃棄物だ。その半減期は、我々のキャリアよりも長いかもしれない。
我々の脳髄は、密閉容器から静かに蒸発するように、目に見えぬ形で失われ続けている。数週間かけて導出された数式が ワンクリックで解けるこの世界で、「考えることをやめる勇気」という、たった一つの選択だけが、ワンクリックでも手に入らない貴重品となった。