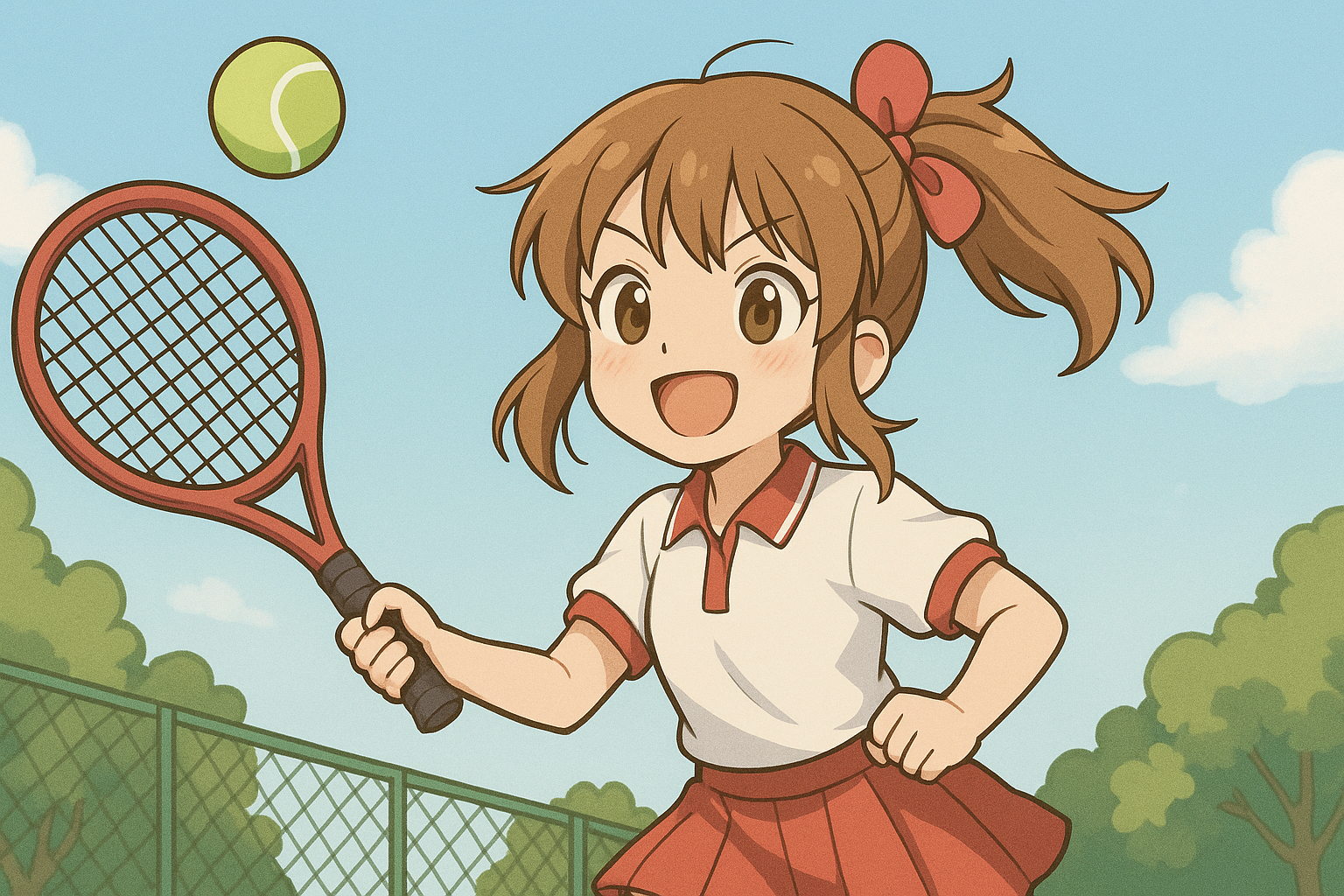
アリとキリギリスと…
時が流れ、人が何かに没頭する瞬間――それは果たして贅沢なのか、それとも必然なのか。人生には潮目というものがある。世間が示す羅針盤が最も強く働きかけてくる時期。出世、転職、結婚、子育て。社会が用意した階段を一段一段上ることが、まるで唯一の正解であるかのように囁かれる。ライフイベントという名の万有引力が、私たちを安定軌道へと引き寄せようとする。
だが、その引力に抗って、ただ純粋に何かに没入する時間を持つことは、果たして愚かなことなのだろうか。
ここで、あの古い寓話を思い出す。アリとキリギリスである。勤勉と怠惰の象徴として語り継がれてきた物語。しかし、この寓話をもう少し異なる角度から眺めてみたい。
アリは資本主義の申し子かもしれない。労働を美徳とし、未来への備えを怠らず、「努力は報われる」という信念のもとに生きる。一方、キリギリスは怠け者の象徴として描かれるが、むしろ資本主義への静かな抵抗者なのかもしれない。今この瞬間の歓びに価値を見出し、蓄積とは別の豊かさを体現する存在として。
カールマルクスはかつて語った。資本主義における労働は「生きるための手段」に過ぎず、「生きることそのもの」ではない、と。
晴れた日の空の下で、ただ無心に身体を動かす瞬間。そこに宿る生の実感は、銀行口座の数字では測れない何かを教えてくれる。それは愚かさではなく、むしろ本質への回帰なのかもしれない。
だが、もちろん、明日から全てを投げ出すわけにはいかない。現実は詩ではない。
結局のところ、アリとキリギリスという二つの極を知った上で、その間のどこかに自分の立ち位置を見つけることが重要なのだろう。善悪の二元論ではなく、無限のグラデーションの中で、自分だけの色彩を見つけること。この古い寓話は、実は勤勉さの教訓などではなく、むしろ多様な生き方への問いかけだったのかもしれない。
極論を知り、その上で自分という存在を人生の主役に据える。そんなバランスの取れた生き方への、密やかな示唆だったのではないか。
没頭する時間を持つことは、決して無駄ではない。それは、自分という物語の著者であり続けるための、静かな抵抗だ。